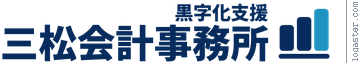いよいよ12月に入り、今年も残りあとわずかです。
個人事業主の方は、そろそそ確定申告の事が気になり出す頃ではないでしょうか。
(「確定申告なんて3月やから、までまだまだ先やんと思われている方もいるかもしれませんが…)
確定申告で一番気になるのはやはり税金です。
「今年はどれくらいの税金になるのか」といったところです。
決算まで残り1ヶ月弱ありますので、今からでも節税できる可能性があります。
今回は、今からできる節税対策について解説したいと思います。
青色申告特別控除を活用する!
青色申告だけど、まだ経理をしっかりやって貸借対照表まで作成していないという方は、ぜひ経理をしっかりやって青色申告特別控除を活用しましょう。
簡易帳簿の場合の青色申告特別控除は10万円ですが、複式簿記で貸借対照表と損益計算書を作成すれば、青色申告特別控除は55万円に増加します。
さらに、電子申告(または電子帳簿保存)で申告すれば、青色申告特別控除は65万円になります。
経理をしっかりやるだけで、55万円も経費が増えるということです。
しかも、お金が出ていくわけでもありません。
今から1年分の経理処理をするのはたいへんかもしれませんが、申告期限までまだ数ヶ月あります。
頑張ればできないこともありません。
事業をされている方は、ぜひ会計ソフトを活用して取り組んでいただきたいと思います。
小規模企業共済に加入する!
小規模企業共済は、国が作った経営者のための退職金制度です。
掛け金は全額所得控除できますので、節税になります。
掛金は1,000円から70,000円まで自由に選択でき、12月に新規加入した場合でも、翌年11月までの掛金前納(年払い)で、1年分の大きな所得控除が受けられます。
つまり最大で70,000円×12ヶ月分=840,000円の経費が使えるということです。
かなりの節税効果が期待できます。
小規模企業共済のメリットは受取時に退職金扱いとなりますので、ほとんど税金が掛かりません。(解約理由によって変わることがあります)
未加入の方で今年儲かっているという方は、ぜひ加入を検討してみましょう。
必要経費をかき集める!
経費を増やせば、もちろん税金は安くなります。
まだまだ計上できていない経費がないか確認してみましょう。
特に自宅を事業に使用している場合は、電気代などの水道光熱費を家事按分することで、経費として計上することができます。
もちろん経費と計上した割合などを税務署に説明できるようにしておかなければいけませんが、事業として使用している部分はしっかりと経費に計上して節税に取り組みましょう。
また、青色申告者の場合、30万円未満の備品などの固定資産については、一括経費に計上することができます。
年明け早々に購入する予定がある場合などは、12月に前倒しで購入することも検討してみましょう。
このように、経費をかき集めることで、節税につながります。
ただし、注意していただきたいのは経費を使うという事は、お金が出ていくということです。
つまり節税した以上に、お金は減っていきます。
手許にお金を残したいのであれば、税金を払うことも必要になります。
お金と税金のバランスを考えた判断が必要になります。
所得控除の計上漏れを確認する!
個人事業主の場合、経費とは別に所得控除の対象となる支払いがあります。
これらを支払うことで、節税につながります。
1つ目は、社会保険料控除です。
国民年金や国民健康保険の支払い漏れはありませんか?
国民年金については、未納分や家族(子供など)の分を支払っても所得控除として控除することができます。
今年、儲かって利益が出ているならば、まとめて支払うことも検討してみましょう。
2つ目は生命保険料控除です。
生命保険は掛けているけど、生命保険料控除の枠が残っている方が見受けられます。
生命保険料控除は保険の種類によって限度額が設けられており、最大控除額は12万円です。
まだ、控除額が残っている場合は保険種類を確認し生命保険への加入を検討してみましょう。
控除額としては少なく節税効果はあまり高くありませんが、塵も積もれば山となるです。
3つめはふるさと納税です。
ふるさと納税は、節税と言う意味では違うかもしれませんが、寄付することで特産品がもらえたります。
税金を払うとなると「払いたくない」となるかもしれませんが、ふるさと納税をすれば、お酒やお肉といった特産品がもらえるので少しはお得感があるように感じます。
本来のふるさと納税の趣旨とは違いますが…
ふるさと納税などのサイトでしっかり自分の限度額を確認してやってみるのもいいのではないでしょうか。
まとめ
個人事業主さんの節税についてまとめてみました。
まだ残り1ヶ月あるから取り組めるというのもあります。
節税のほとんどが、お金の支出を伴います。
節税した結果、お金が激減して生活できないとなってしまっては意味がありません。
しっかり資金繰りも考えたうえで、節税に取り組みましょう!