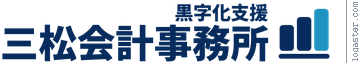おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
令和2年4月1日から「改正民法」が施行され、契約のルールが大きく見直されます。
今回は、不動産オーナーに影響のある不動産賃貸における原状回復義務や敷金のルールについて見ていきたいと思います。
通常損耗は借り手に原状回復義務なし!
不動産賃貸契約が終了した時、借り手は、物件を元の状態(現状)に戻して貸主である大家さんなどに返す原状回復義務があります。
賃貸マンションに住んでいる私も、なるべく傷つけないように気を使っています。
さて、旧民法では原状回復の範囲に範囲について、明文化された規定がなかったため、トラブル発生時には判例の積み重ねによって法的な解決が図られてきました。
改正民法では、通常損耗や経年変化については、借り手に原状回復義務がないことが法律上明確になりました。
通常損耗や経年変化に当たる例としては次のようなものが該当します。
・家具の設置による床、カーペット等のへこみ
・テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ
・壁等の画びょう、ピン等の穴
・鍵の取り換え
・地震で破損したガラス
また、通常損耗・経年変化に当たらない例は次のようなものが該当します。
・引っ越し作業で生じた引っかきキズ
・壁等のくぎ穴、ネジ穴
・たばこのヤニ、臭い
・落書き等故意による毀損、飼育ペットによるキズ、臭い
ただし、貸主と借り手が合意すれば、賃貸借契約において、「通常損耗や経年変化の場合についても借り手が原状回復の義務を負う」という「補修特約」を設けることが認められています。
不動産オーナーとしては、「補修特約」を設けることで原状回復義務の範囲を明確に定めておくことが、後日のトラブル防止につながるのではないでしょうか。
敷金は原則として返還しなければなりません!
契約時に借り手が貸主に支払った敷金についても旧民法で明文規定がありませんでしたが、改正民法では、敷金について「保証金などその名称にかかわらず、家賃の滞納等に備えて担保として借り手が貸主に交付する金銭」と定義を明確にしました。
つまり、不動産賃貸の契約終了後には、貸主は敷金を返還しなければなりません。
ただし、家賃の滞納分や損害賠償金、原状回復費用などは、敷金から差し引くことができます。
借り手に家賃の未払いがあるときなどは、敷金から滞納家賃を差し引くことができるため、不動産オーナーにとっては敷金は非常に重要なものとなります。
債務保証のルールの見直し!
家賃の不払いなどに備えて、賃貸契約において保証人(個人)を求める場合は、「保証人が支払いの責任を負う金額の上限額(極度額)」を具体的に「金〇〇円」などと明瞭に定め、書面に必ず記載しなければなりません。
旧民法では、借り手の落ち度で貸家が焼失した場合に、保証人に予想外の巨額の損害賠償請求がされることがありましたが、改正民法では保証人保護の規定が定められたということです。
賃貸借契約で保証人を求める場合は、書面で明確に極度減額を定める必要があります。
また極度減額の定めがない保証契約は無効になるので注意が必要です。
新ルールは令和2年4月1日以後の契約から適用されます!
新ルールはいつから適用されるのかというところですが、令和2年4月1日以後の契約から適用されます。
つまり、施行日(令和2年4月1日)前に締結された契約には旧民法が適用され、施行日以後に締結された契約には改正民法が適用されるとういうことです。
また、施行日後に借り手と貸主の合意によって契約を更新した場合には、改正民法が適用されます。
まとめ
不動産の賃貸契約のルールが変わりますということで、不動産オーナーに影響がありそうな改正項目をピックアップしてみました。
不動産オーナーの方は、契約の見直しを行うとともに、気になる点は弁護士や司法書士といった契約のプロに相談してみるのがいいのではないでしょうか。